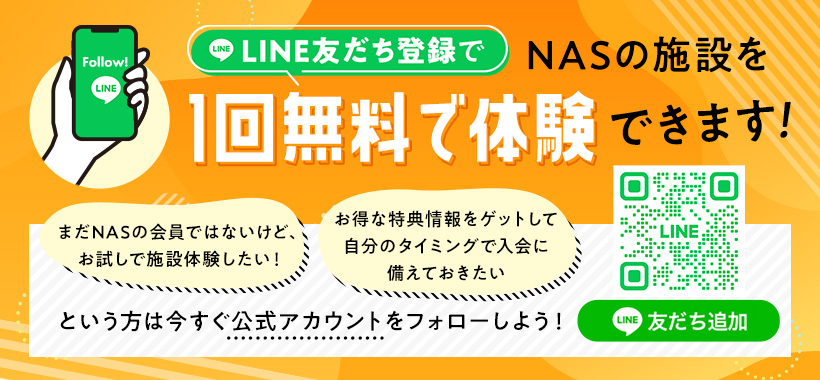一日一食ダイエットとは?一日一食のリスクやデメリットも解説

一日一食ダイエットとは、1日に摂る食事を1回だけに制限する減量方法です。単純に考えると摂取カロリーを大幅に減らせるため、短期間での体重減少効果を期待する方も多いでしょう。しかし、実際には一日一食にすると栄養バランスが崩れやすく、便秘や筋肉量の低下、リバウンドのリスクが高まるため、おすすめできないダイエット方法です。
この記事では、一日一食ダイエットで起きるさまざまなデメリットや、食事回数を減らす場合のポイント、三食を摂りつつダイエットをするコツを解説します。
目次
Toggle一日一食ダイエットとは

一日一食ダイエットとは、1日の食事回数を1回に制限するダイエット法のことです。朝食・昼食・夕食のいずれか1回のみ食事を摂り、そのほかの時間帯は水分補給などにとどめる方法が一般的です。
食事回数を減らすことで、1日の総摂取カロリーを抑えることができるため、比較的短期間で体重減少の効果が得られるとされています。また、食事にかかる時間や費用を削減できること、空腹時間を長く保てて食後の倦怠感を覚えにくいといった点も、注目される理由の1つです。
結論:一日一食ダイエットは推奨できない
結論から言えば、一日一食ダイエットはおすすめできません。一見すると摂取カロリーを抑える効果的な方法に思われます。しかし、必要な栄養素が不足しやすく、体調を崩す危険性が高まるため、避けたほうがよいでしょう。
女性の場合は極端に食事量を減らすことでホルモンバランスが乱れて月経不順が生じるケースもあります。さらに、一時的な体調不良にとどまらず、長期的な健康リスクにつながる恐れもあるため、推奨できないダイエット方法です。
健康的に痩せるためには、一日一食や断食などの極端な食事制限ではなく、バランスのとれた食生活と運動、生活スタイルの見直しが必要です。
一日一食ダイエットのデメリット

一日一食ダイエットは、メリットよりリスクやデメリットのほうが多いダイエット方法と言えます。以下では、一日一食ダイエットのデメリットを紹介するので、これからダイエットを考えている方はぜひ参考にしてください。
リバウンドしやすく痩せにくい体になる恐れがある
一日一食ダイエットのような極端な食事制限によって飢餓状態に陥ると、生理的な防御反応として体が脂肪を蓄えやすくなります。これは「ホメオスタシス(恒常性)」と呼ばれる体の機能が働くためです。ダイエット終了後に通常の食事に戻しただけでリバウンドする可能性が高まる点がデメリットです。
また、1日の食事回数を減らすと必要な栄養補給が難しくなり、特に筋肉のもととなるタンパク質が不足しやすいのも問題です。タンパク質不足の状態が続けば、筋肉量が減少して基礎代謝が落ち、代謝で消費するカロリーが減ることで、痩せにくく太りやすい体質になるおそれがあります。
基礎代謝の低下によって、同じ量を食べても脂肪量が増えやすくなるため、ダイエット前より体重が増えてしまうケースもあるでしょう。リバウンドを防ぐには、極端な食事制限を避け、筋肉を維持しながら体重を落とす方法を選ぶことが大切です。
便秘を起こす可能性がある
一日一食ダイエットでは、食事の量や回数が大幅に減少するため、自然と水分や食物繊維の摂取量も少なくなりがちです。特に便通に必要とされる水溶性食物繊維やマグネシウムの摂取量が不足すると、腸のぜん動運動(内容物を押し出す動き)が鈍り、便秘になりやすくなります。
また、生理的な反応として、食事をすると腸が刺激されて排便が促されます。しかし、食事の機会が少ないと排便の刺激がなくなるため、便の回数が減って腸の中に便が溜まりやすくなる点もデメリットです。
便秘が続くと、肌荒れや腹部膨満感、集中力の低下などの不快な症状を引き起こすこともあり、日常生活の質に悪影響を及ぼす可能性があります。腸内環境の悪化は免疫力の低下にもつながるため、ダイエット中でも便秘にならないように三食をしっかり食べるほうがよいでしょう。
血糖値が急に上がりやすくなる
一日一食ダイエットでは、空腹時間が長時間続いた後に一日分の食事を一気に摂るため、血糖値が急上昇しやすいことが大きなデメリットです。
大量のエネルギー摂取によって血糖値が急激に上がると、体内ではインスリンが多量に分泌され、血中のブドウ糖を脂肪として蓄積しようとします。結果、脂肪が増えやすくなり、太りやすくなります。
さらに、一日一食を続けているとどうしても強い空腹感をおぼえやすくなり、高糖質・高脂質の食べ物を大量に摂りたくなるのも危険なポイントです。飢餓状態から一気に高糖質・候脂質の食事を摂取すると、血糖値が急上昇・急降下する血糖値スパイクに陥るリスクがあります。
血糖値スパイクは、血管を傷つけて動脈硬化を促進し、心疾患・脳卒中などのリスクを高めるため、生活習慣病の要因になる現象です。一日一食という極端な食事制限では、血糖コントロールが難しくなるため、リスクが高くなる点も問題と言えます。
ストレスで食べすぎるリスクがある
一日一食しか食べられないという状況が、精神的なストレスにつながりやすい点もデメリットです。特にこれまで三食食べていた方にとっては、食べたい気持ちを長時間我慢し続ける必要があるため、空腹による不快感やイライラが募りやすくなります。
ストレスが積み重なると、反動でドカ食いをしてしまったり、甘いものや高脂肪の食品に手が伸びやすくなったりすることもあります。過食によって、かえってダイエット効果が損なわれてしまうという本末転倒の結果を招くこともあるでしょう。
さらに、慢性的なストレスは自律神経やホルモンバランスにも影響を及ぼし、睡眠の質を低下させたり、食欲を乱したりする要因にもなります。無理な制限によってストレスを感じるようなダイエット方法は、継続性にも乏しく、長期的な健康管理には向いていません。
長期的に見て疾患リスクが高まる可能性がある
一日一食ダイエットを、長期的に続けた場合には、健康を損なうリスクが高まると指摘されています。
米国国民健康栄養調査の結果では、朝食を抜く人は心血管死リスクが40%高くなり、昼食を抜く人や夕食を抜く人は全死亡(あらゆる原因による死亡)リスクが12~16%高いという結果が判明しました。どのタイミングで食事を抜いても、健康を損なうリスクは高まります。
さらに、一日一食しか食事を摂らなかった場合、全死亡リスクは30%、心血管死のリスクは83%も高まることも分かりました。
出典:スポーツ栄養Web「食事を抜くと寿命が縮まる!米国国民健康栄養調査の縦断解析 1日1食では心血管死が83%UP」
また、栄養不足が続けば、体力や気力が加齢により衰える「フレイル」や、筋力が低下する「サルコペニア」の症状が早期に現れるリスクもあります。
米国国民健康栄養調査の結果では、一食あたりの食事時間を最低でも4.5時間以上空け、三食を摂れば健康リスクが低下するという結果が出ています。健康的に痩せるためにも、バランスの取れた食事を決まった時間に摂るのが大切です。
どうしても食事回数を減らす場合のポイント

ダイエット目的でなくても、時間がなくて食事が摂れないときや、食事が欲しくないと感じるときはあります。三食をしっかり食べるのが健康に良いというのは前提として、どうしても食事回数を減らす場合、1日に必要な栄養を摂取できるようにするのが大切です。
人間に必要なエネルギーおよび三大栄養素のうち、1日に必要な栄養素は以下の通りです。
・身体活動レベル「ふつう」の場合必要な栄養素
| 年齢 | 18~29歳 | 30~49歳 | 50~64歳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| エネルギー(kcal) | 2,600 | 1,950 | 2,750 | 2,050 | 2,650 | 1,950 |
| たんぱく質(g)※推奨量 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| 炭水化物(食事摂取量比目標量) | 50~65% | |||||
| 脂質(食事摂取量比目標量) | 20~30% | |||||
ほかにも、ビタミン類や飽和脂肪酸、食物繊維、ミネラルなどを摂取する必要がありますが、まずは必要なカロリーを摂取できており、PFCバランス(三大栄養素の摂取バランス)に問題がない食事を目指すとよいでしょう。
三食を摂りつつダイエットをするときのポイント
極端な食事制限をするのでなく、一日三食をしっかり摂りながら無理なく減量を目指すことは、健康的なダイエットの基本です。ここでは、日常生活に取り入れやすく、効果的なダイエットの3つのポイントをご紹介します。
食事はよく噛んでゆっくりと食べる
早食いは満腹感を得る前に過剰に食べてしまう原因になります。食べすぎを防ぐためにも、よく噛んでゆっくり食べ、満腹中枢が刺激されるような食べ方をするのが大切です。一口あたり30回を目安に噛めば、食事にかける時間が自然と長くなり、早食いによる過剰摂取を防ぎやすくなります。
よく噛むと、血糖値の急上昇も抑えられ、肥満や糖尿病の予防につながる点もメリットです。また、噛むことで脳が刺激され、集中力が上がり、ストレスも軽くなります。よく噛んで食べる習慣は、単なる食べすぎの防止だけでなく、健康管理の面でも大切です。
有酸素運動と無酸素運動を組み合わせる
食事による摂取カロリーを消費し、筋肉を維持するためには、運動が不可欠です。特に、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動と、筋トレに代表される無酸素運動の両方を取り入れることで、効率的に脂肪を燃焼させることができます。
有酸素運動は脂肪をエネルギーとして消費しやすく、体についた脂肪を落とすのに有効な運動方法です。一方で、無酸素運動によって筋肉をつけると基礎代謝が上がり、太りにくい体質につながります。
適度な運動により運動不足が改善すれば、ストレスも解消され、適度な疲れによりぐっすりと眠りやすくなります。運動習慣がなかなか身につかない場合は、近隣のスポーツジムなどを活用するとよいでしょう。
睡眠をしっかりとる
睡眠時間が不足すると、食欲を高めるホルモン(グレリン)が増加し、反対に食欲を抑えるホルモン(レプチン)が減少します。また、夜更かしが続くと体内時計が狂い、同様にグレリンが増加してレプチンが減少します。その結果、間食が増えたり、つい食べすぎてしまうことが多くなるため、生活リズムの乱れはダイエットの大敵です。
規則正しい睡眠はホルモンバランスの維持を助け、衝動的な食べすぎを防いでくれる要素です。質の良い睡眠を確保するために、就寝前のスマートフォン使用を控える、寝室の環境を整える、就寝・起床時間を一定に保つなどの工夫をしましょう。
まとめ
健康的に痩せるためには、一日一食のような極端な食事制限はおすすめできません。健康を維持しつつ効果的に痩せるには、毎日の食事を規則正しく三食摂り、よく噛んでゆっくり食べることが重要です。さらに、有酸素運動と筋トレを適度に組み合わせ、睡眠をしっかり取ることで、基礎代謝を維持しながら体重を減らすことができます。無理のない方法で、長期的に健康を保ちながらダイエットを進めましょう。
適度な運動を行うためには、スポーツジムを利用するのも効果的です。スポーツクラブNASには、運動や食事指導の専門家であるトレーナーが在籍しています。良質な食事と運動習慣を継続したいと思っている方は、ぜひお近くのスポーツクラブNAS店舗にご相談ください。
関連記事Related Articles

健康的に痩せる方法とは?運動を習慣にすればダイエットは楽しくなる
世の中にはあらゆるダイエット法があり、いろいろ試してみたという人も多いでしょう。しかし痩せたいと思ってダイエットしているのに、思ったように痩...
ダイエット 栄養・食事
食べ過ぎた次の日はどうしたらいい? 対処法の紹介とダイエットに大切な考え方
ダイエットでは常に食事に気をつけ、食べすぎを防ぐことが基本中の基本です。ところがダイエット中であるにもかかわらず、ついつい食べすぎてしまうこ...
ダイエット 栄養・食事
糖質による血糖値の急上昇を抑えるおすすめの食べ物|食べ方も解説
糖質は人が生活していくうえで体のエネルギー源として働くため、なくてはならない栄養素です。しかし、摂りすぎると肥満、糖尿病といった病気のリスク...
栄養・食事
ダイエットでカロリー制限をする際の目安|基礎代謝についても解説
食事を意識したダイエットにおいて、糖質やエネルギーを摂取しすぎるとなかなか効果が出ないことがあります。糖質は炭水化物を構成する主要な成分で、...
ダイエット 栄養・食事
ダイエットのチートデイは本当に効く? 正しいやり方と注意点を徹底解説
ダイエット中に、食べ物をたくさん食べられる「チートデイ」。チートデイはダイエットに効果的と聞きますが、たくさん食べても本当にいいのでしょうか...
栄養・食事
糖質を取りすぎた次の日はどうすればよい?調整のコツを解説
糖質は、お米・麺・パン・イモなどの主食、甘い菓子類、果実などに多く含まれる、脳や身体のエネルギー源として重要な栄養素です。ただし、取りすぎる...
栄養・食事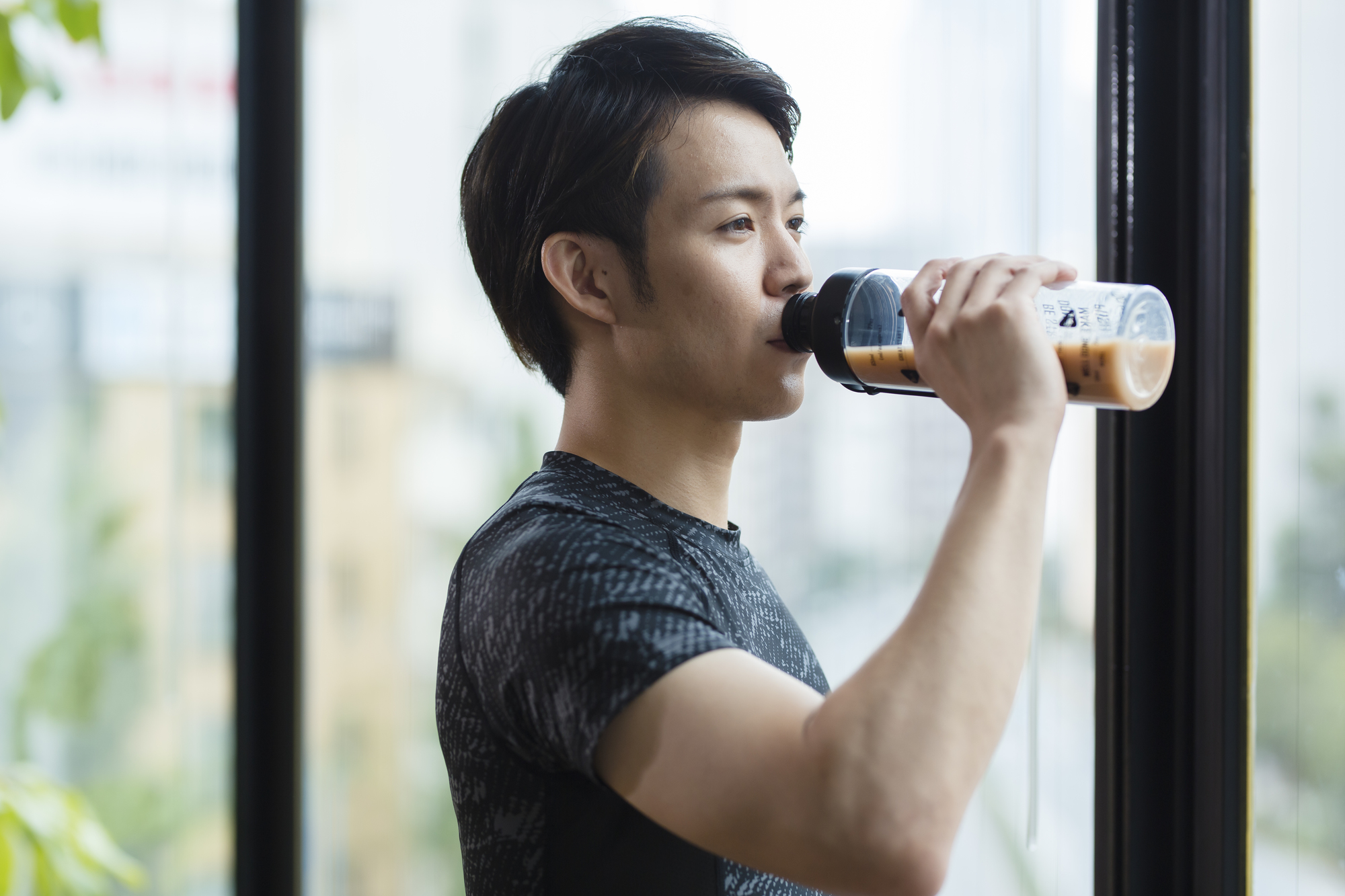
プロテインを飲むタイミングはいつ? ベストな時間と飲み方を解説
プロテインは、適切に摂取すると筋トレの効果を高め、ボディメイクを効率的に行うことができる重要な食品です。体づくりのためにプロテインを取ろうと...
栄養・食事
理想的な体脂肪率とは? 健康的に体脂肪率を落とす方法を詳しく解説
ダイエットのときに目安となるのが体脂肪率です。この記事では、体脂肪率の落とし方について深堀して解説します。この記事を読めば、体脂肪率とは何か...
栄養・食事